校長ブログ
AIの自己改良
2025.08.16
EdTech教育
8月16日
シンガポールにあるEXPO国際会議場で開催されたAIの国際学会に関する報道を目にしました。そこには、メタ社(米)のチーフAIサイエンティストであるヤン・ルカン氏が予告なしに現れたことで、ブース前に50人を超える若い研究者たちが集まる光景が描かれていました。ルカン氏は、AGI(汎用人工知能)の研究における世界的権威であり、多くのエンジニアたちの憧れの存在です。
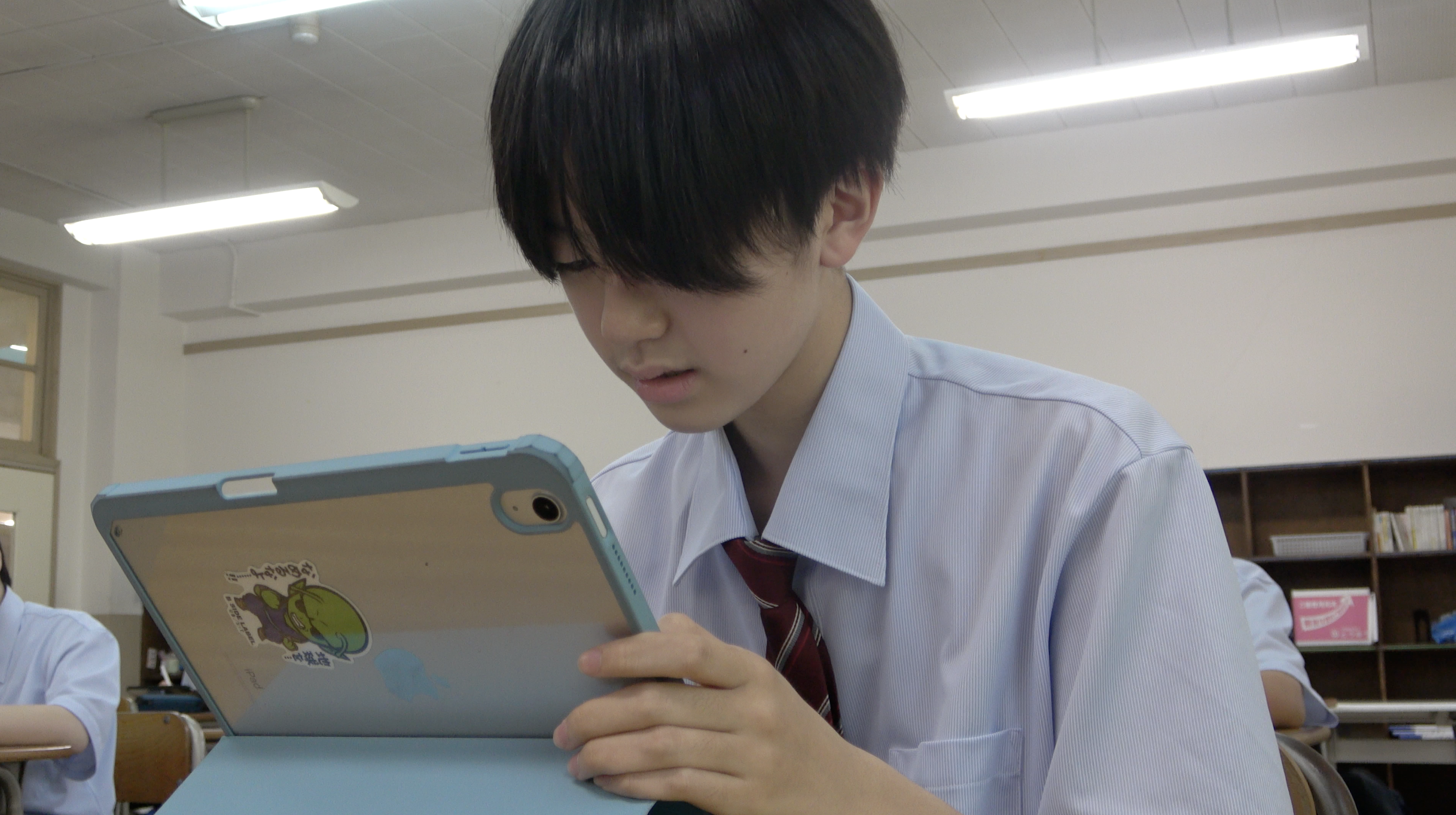
「今、何を研究すべきか」という問いに対して、ルカン氏は「大規模言語モデルには取り組まない方がよい」と、意外な言葉で応じています。これは、教育関係者にとっても大きな示唆を含んでいます。ChatGPTをはじめとする生成AIの基盤である大規模言語モデルは、膨大な知識と計算能力を誇ります。しかし、空間認識や因果推論といった本質的な知性―例えば、落ちるリンゴを見て万有引力を発見するような力―には、まだ到達していないのです。彼は、赤ちゃんのように世界を観察し、物理現象を理解するAIの開発に乗り出しているそうです。
一方、オープンAIのサム・アルトマンCEOは、AGI(汎用人工知能)こそが人類の未来を左右する技術であると確信し、巨額の資金を投じています。その最終形態ともいえるASI(人工超知能)、つまり、人間の知性をはるかに超え、自らを進化させる知能が、すでに視野に入り始めています。実際、2027年にAGIが実現し、その年の後半にはASIに到達するというシナリオを描いた「AI 2027」というレポートも公開されました。
このような未来は、フィクションではなく、現実の延長線上にあるのだとすれば、どのような視座で子供たちの学びを構築すべきでしょうか?AIが高度化し、あらゆる情報を処理できるようになったとしても、「なぜ学ぶのか」「どのように人と関わるのか」といった価値観や倫理観、想像力は人間固有の営みです。超知能がすべてを最適化しうる未来においてこそ、対話する力、多様性を受け入れる力、自分の言葉で語る力がいっそう重要になります。
また、AI開発の急速な進展は、「勝者総取り」の原理を強め、企業や国家間の投資競争を激化させています。日本の国家予算を超える額が、データセンターへの投資として動いているという事実も重く受け止める必要があります。エリック・シュミット氏が指摘するように、安全性や倫理面での国際的なルールづくりが急務であることは、教育の現場でも子どもたちに伝えるべき課題です。
ユヴァル・ノア・ハラリ氏は「私たちが今持っているAIは、世界を完全に変革するのに十分なものだ」と語っています。その変化の中で生きる子どもたちに、どのような知性と感性を育てていくのか?教育の役割は、単なる知識の伝達ではなく、未来への責任を育むことに他なりません。AIが進化しようとも、人間が人間らしく生きることこそが、教育の核心であり続けると感じるのは私だけではないと思います。
